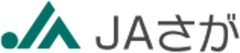えんどう豆とそら豆
えんどう豆とそら豆の種まき
えんどう豆やそら豆の栽培は、九州地方の場合、遅くとも11月いっぱいまでに種まきを終えるようにします。寒い時期に芽や本葉が小さいと、枯れてしまうからです。
なお、畑で栽培する場合は、連作を嫌うので、最低3年以上間をあけること。また、酸性の土壌に弱いため、石灰を施して栽培するよう心がけましょう。
作業手順
-
1
 準備するもの、えんどうの種または、そら豆の種、支柱用フレーム付丸型プランター(市販の支柱がセットできます)、培養土
準備するもの、えんどうの種または、そら豆の種、支柱用フレーム付丸型プランター(市販の支柱がセットできます)、培養土
※畑の場合は、石灰や有機石灰を準備。 -
参考
 豆類は特に酸性の土壌を嫌います。酸度調節のために、一般的に使われる苦土石灰で、1平方メートルに対し約100g〜150gを、種をまく2週間ほど前に施す。家庭菜園で人気がある有機石灰は、種まきの直前でも大丈夫。約200gを、大人の手の平で軽く掴んだ一回が約50gなので、4回を目安に施す。
豆類は特に酸性の土壌を嫌います。酸度調節のために、一般的に使われる苦土石灰で、1平方メートルに対し約100g〜150gを、種をまく2週間ほど前に施す。家庭菜園で人気がある有機石灰は、種まきの直前でも大丈夫。約200gを、大人の手の平で軽く掴んだ一回が約50gなので、4回を目安に施す。 -
2
 今回はプランターを使った栽培。プランター栽培は、土を変えれば連作障害の心配がなく、過湿に弱い豆類に対し、水分調整がしやすいメリットがある。
今回はプランターを使った栽培。プランター栽培は、土を変えれば連作障害の心配がなく、過湿に弱い豆類に対し、水分調整がしやすいメリットがある。
ワンタッチで支柱(別売り)をセットできるので、つる性の植物に最適。 -
3
 そこ網をセットし、水抜き穴のふたをはずす。
そこ網をセットし、水抜き穴のふたをはずす。 -
4
 培養土を入れ、表面を平らに整地する。芽が出た後で土寄せを行うので、鉢のふちから多めにウォータスペースを取る。
培養土を入れ、表面を平らに整地する。芽が出た後で土寄せを行うので、鉢のふちから多めにウォータスペースを取る。 -
5
 ひとつのプランターで栽培できるのは一箇所です。育てたい豆の種類を決める。
ひとつのプランターで栽培できるのは一箇所です。育てたい豆の種類を決める。
※鞘ごと食べる(絹さやえんどう)、中の実だけ食べる(実えんどう)、中の実も皮も食べる(スナックえんどう)。または、そら豆 -
6-えんどう豆のまき方
 過湿に弱いえんどう類の種蒔きは、一箇所に3〜4粒。三角や四角になるよう等間隔に置き、種が見えなくなる程度に指で軽く押さえ、なでる程度にふく土をする。
過湿に弱いえんどう類の種蒔きは、一箇所に3〜4粒。三角や四角になるよう等間隔に置き、種が見えなくなる程度に指で軽く押さえ、なでる程度にふく土をする。
※畑に蒔く場合、各箇所は約30〜35cm間隔。 -
6-そら豆のまき方
 そら豆を蒔く時は、種の方向に注意する。一箇所に3粒。根が出る、黒い筋(一般におはぐろと呼びます)の部分を真下にして、深さは、土の表面から種が少し見える程度に埋め、ふく土はしない。
そら豆を蒔く時は、種の方向に注意する。一箇所に3粒。根が出る、黒い筋(一般におはぐろと呼びます)の部分を真下にして、深さは、土の表面から種が少し見える程度に埋め、ふく土はしない。
※畑に蒔く場合、各箇所は約40cm間隔。 -
7
 最後に水を、プランターの底から出るまでたっぷりと与える。
最後に水を、プランターの底から出るまでたっぷりと与える。
※管理の仕方は、数日に一回、土の表面が乾いてきたら与える程度。過湿に弱いので与え過ぎに注意する。
春に食べる豆類2間引き〜支柱立て)
芽が出て、本葉が5枚ほどの時期に、一番生育状態の良い茎1本だけを残し間引きます。
また、ある程度の高さに育ったころ、倒伏防止のための支柱を立てます。
間引きの手順
-
8
 間引きは、発芽してから本葉が5枚程度出る頃までに行う。
間引きは、発芽してから本葉が5枚程度出る頃までに行う。
3株あるうち、一番生育状態の良い1株だけ残す。2株を引き抜く。 -
9
 間引き後、土寄せを行います。風などで倒れないよう株の周りに培養土を加え、根元を押さえる。
間引き後、土寄せを行います。風などで倒れないよう株の周りに培養土を加え、根元を押さえる。
支柱立ての手順
-
10
 準備するもの。プランターに付属のリング一つと、支柱支え(留め具)4つ、市販されている支柱8mmを4本と、11mm1本、ミラーテープ一巻き。
準備するもの。プランターに付属のリング一つと、支柱支え(留め具)4つ、市販されている支柱8mmを4本と、11mm1本、ミラーテープ一巻き。 -
11
 最初に、支柱支え(留め具)をプランター4カ所に対角線上にセットする。
最初に、支柱支え(留め具)をプランター4カ所に対角線上にセットする。 -
12
 次に、8mmの支柱4本をプランターに垂直に立てる。プランターの底まで差し込む必要はありません。
次に、8mmの支柱4本をプランターに垂直に立てる。プランターの底まで差し込む必要はありません。
土に軽く(約4〜5cm)差し込み、支柱支え(留め具)にカチッと音がするようはめ込む。 -
13
 リングを支柱に取り付ける。支柱の最上部から約5〜6cm下部に、カチッと音がするようはめ込む。
リングを支柱に取り付ける。支柱の最上部から約5〜6cm下部に、カチッと音がするようはめ込む。 -
14
 取り付けたリング中心の穴に11mmの支柱を通し、土に軽く差し込む。
取り付けたリング中心の穴に11mmの支柱を通し、土に軽く差し込む。 -
15
 倒伏防止のため、また、アブラムシ飛来を軽減させるため、ミラーテープを支柱に巻き付ける。
倒伏防止のため、また、アブラムシ飛来を軽減させるため、ミラーテープを支柱に巻き付ける。
つるを持たない豆類を、支柱と横方向に巻くテープで保護する。 -
16
 豆類の成長に合わせ、巻きつけるテープを増やす。最終的に三カ所ほど。
豆類の成長に合わせ、巻きつけるテープを増やす。最終的に三カ所ほど。 -
17
 葉が黒くなっている箇所がありましたが、今期の冬(2009年〜2010年)は寒さが強かったための障害で、心配はいりません。
葉が黒くなっている箇所がありましたが、今期の冬(2009年〜2010年)は寒さが強かったための障害で、心配はいりません。
※管理の仕方は、数日に一回、土の表面が乾いてきたら与える程度。過湿に弱いので与え過ぎに注意する。日中の日差しがながる当たる場所に置く。
春に食べる豆類3(枝の整理・追肥・土寄せほか)
背丈が3〜40cmほどの高さになったら、枝の整理と追肥、土寄せを行います。
さらに約一ヶ月後、花が咲き背丈が50〜60cmになった頃に、先端を切り落とす「ピンチ」をします。
またさらに約一ヶ月後、サヤが大きくなり実の重みで垂れ下がり、サヤにツヤが出ると収穫の目安です。
※枝の整理・追肥・土寄せほか
※生長点を止めるピンチ作業
-
18
 生育の良い枝を3本残し、そのほかの枝やわき芽を根元から切り取る。
生育の良い枝を3本残し、そのほかの枝やわき芽を根元から切り取る。 -
19
 配合肥料を20〜30g、株の周りに施す。
配合肥料を20〜30g、株の周りに施す。 -
20
 背丈が高くなっても株が倒れないように、株の周りに土を入れ軽く押さえる。
背丈が高くなっても株が倒れないように、株の周りに土を入れ軽く押さえる。 -
21
 生育に合わせ、支柱の周りに2段目のテープを巻く。この後も、生育に合わせテープを巻く。
生育に合わせ、支柱の周りに2段目のテープを巻く。この後も、生育に合わせテープを巻く。 -
22
 花が咲き背丈が50〜60cmになった頃に、先端を切り落とす「ピンチ」をする。
花が咲き背丈が50〜60cmになった頃に、先端を切り落とす「ピンチ」をする。
ピンチを行うことで、花や実の方へと栄養が行き届く。
※収穫
-
23
 ピンチ作業を終え、花が落ち、サヤが大きくなっていきます。
ピンチ作業を終え、花が落ち、サヤが大きくなっていきます。
最初は、そら豆の由来どおり、空をめがけて大きくなっていきます。(写真左側)
その後、実の重みでサヤが垂れ下がり、サヤの表面にツヤが出ると収穫の目安です。(写真右側) -
24
 収穫する際は、サヤの根元からハサミで切り取ります。
収穫する際は、サヤの根元からハサミで切り取ります。 -
25
 ビールのおつまみに、サヤから実を取り出し塩ゆでするといいですね。
ビールのおつまみに、サヤから実を取り出し塩ゆでするといいですね。
次々と出てくる側枝も、花や実に養分が届くようにピンチ作業をしましょう。
今回、誘引にミラーテープを使用したことで、キラキラした光を嫌う、アブラ虫の被害にほとんどあいませんでした。